いつ頃から言われる様になったのかは分かりませんが、
「にゃん・にゃん・にゃん」という語呂から2月22日は【猫の日】だそうです。
なので、『猫にまつわる事で何か書けないかな?』と考えていたら、
自分が初めて買ったCDの事を思い出しました。
なので、今回はそのことについて書いてみます。
自分が初めて購入したCDは筋肉少女帯の「サボテンとバントライン」という曲なのですが、この曲は昔、あるテレビCMで使用されていました。
そして、当時の自分(10代)はこの曲を聞いたとき『うわ!この曲良いな!』と思ったのですが、CMの画面の片隅に表記された【「サボテンとバントライン」筋肉少女帯】を見て『変な曲のタイトルだな~。あと、筋肉少女帯なんて名前、聞いたことないよ』ぐらいの感覚でした。
でも、この曲の事が気になったので、
そのCDを購入して親のおさがりのCDラジカセで聴いたら、
「サボテンとバントライン」の【バントライン】とは曲中に登場する少年の飼いネコの名前だとわかりました。
なので、当時の自分は『【バントライン】なんて、変な名前だな~』ぐらいの感覚でしたが、この思い出が『今日みたいな【猫の日】にはちょうどいいネタかも?』と思ったので、今回はその思い出について書いてみました。
*記事を読んでいただき、ありがとうございます。
只今、グループの【ランキング】に参加をしているので、
お手数ですが上記バナーをクリックをしていただけると励みになります。
あと、「サボテンとバントライン」がきっかけで、
「筋肉少女帯」の曲を色々と聴くようになりましたが、
いちばん好きなのは「くるくる少女」です。


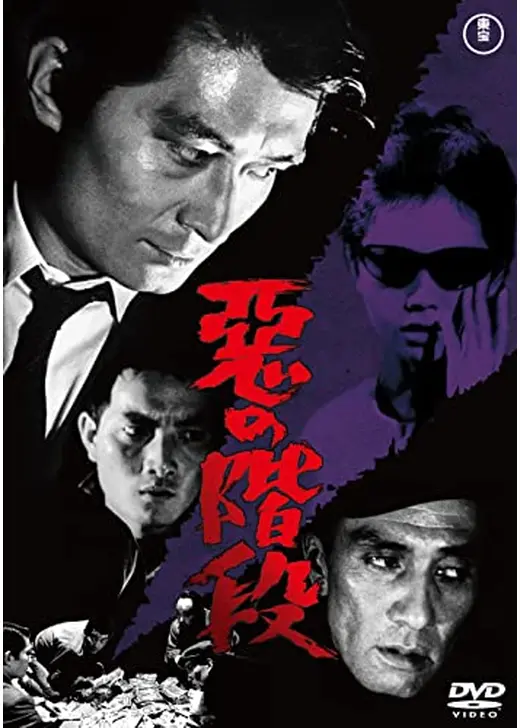








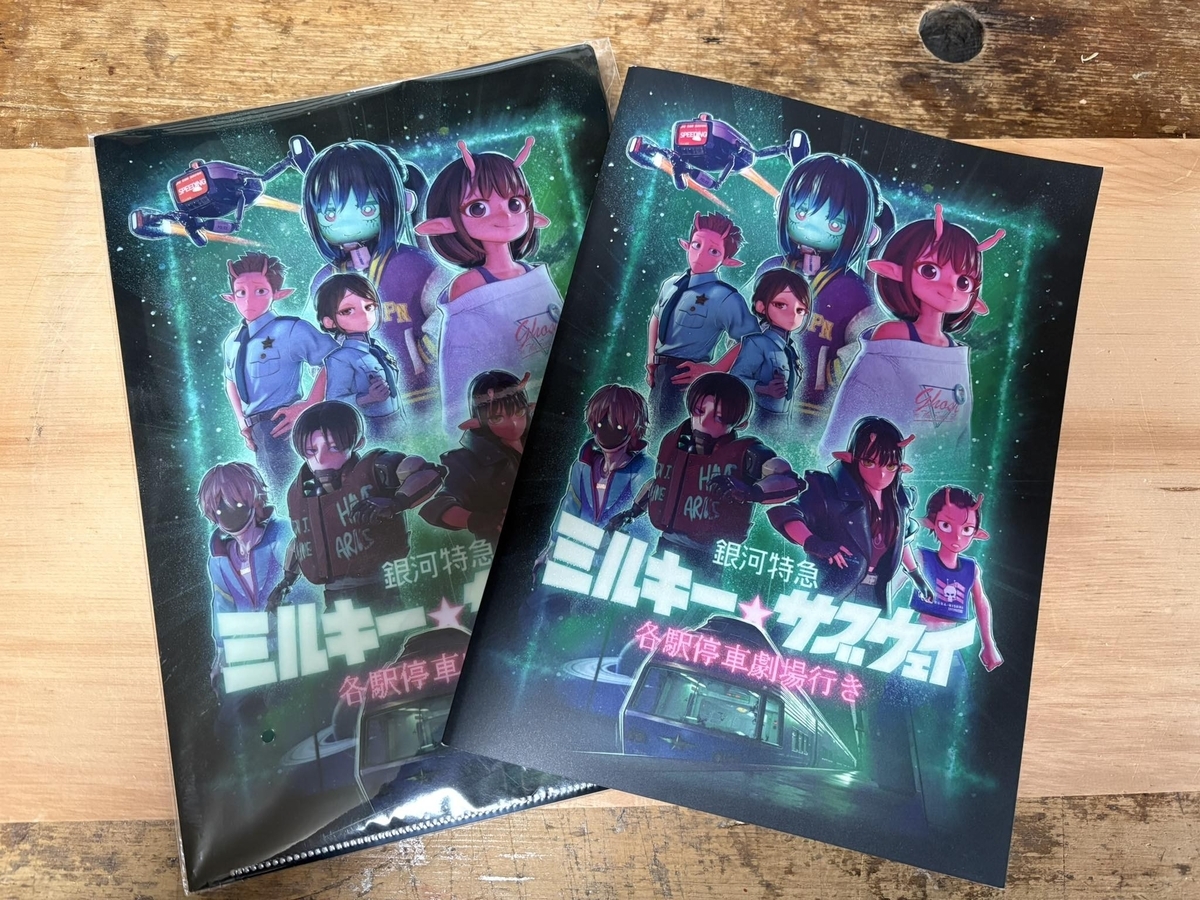





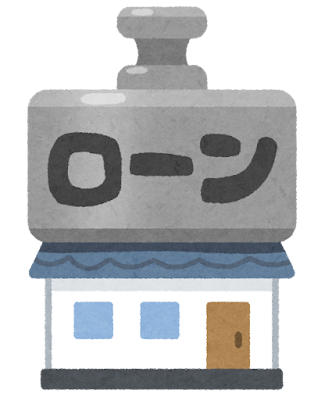
![マネー・ショート 華麗なる大逆転 [DVD] マネー・ショート 華麗なる大逆転 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/511x3LtG7AL._SL500_.jpg)








